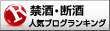|
2019/4/1
|
|
お酒を呑んでもストレスは解消できない |
|
酒は百薬の長ではありません。なぜ百害あって一利なしのアルコールが百薬の長と言われてしまうのか?理由は簡単です。お酒を呑むと頭の神経が麻痺して、疲れや寒さもとれて気分がよくなるからです。 眠くなりますがこれは頭の神経が毒に耐えきれずに眠れと脳に指令をだしてしまうからです。有毒なアルコールを分解するために寝ることが必要だと感じるためです。 寝つきは良くても、覚醒して目が覚めてしまうのもこのためです。体がアルコールを分解できず起きていないと何もできないと脳が命令して起きてしまうのです。 ストレス緩和、睡眠作用、血流促進、食欲増進、コミュニケーション。 ストレスの緩和。お酒を飲んでもストレスは解消できないです。ただの現実逃避です。次の日になれば余計にストレスが溜まってしまいます。アルコールを分解するのにかなりのエネルギーを消費します。 アルコールを飲んで次のすっきり目が覚めないのはこのためです。よく眠れないのでストレスが余計に溜まり、次の日の夕方になればストレス、疲れが溜まってまた飲みたくなります。飲めば飲むほどストレスがたまり睡眠の質が悪くなります。ストレス緩和どころか、ストレスが増進してしまうのです。いつもいらいらするのも睡眠が原因です。 睡眠の質はよくなるように感じますが全く違います。アルコールを飲んで寝てもすぐに目覚めてしまいます。眠くなる理由は、アルコールという毒により、頭の神経がダメージを受けたために眠くなるのです。睡眠作用のために毒を飲む愚かな人はいないでしょう。疲労は回復どころかますます疲れてしまい飲みたくなってしまうのです。 血流の促進。これは毒をよりよく解毒するために血流が良くなるように見えるのです。本来必要のないことをやっているから余計に疲れるのです。血流が良くなるのではなく、アルコールを解毒するために血流が良くなっているのです。 食欲増進。これも毒を解毒するためにエネルギーが必要になってくるから食べてしまうのです。 コミュニケーション。取引先、上司と飲んでも酒は不味いだけです。いちいち気を使って飲んでも苦しいだけです。同僚、友人酔っ払って同じことを言ってもバカらしいです。 毒しか入っていない上に、アルコール依存症になってしまう。 断酒のカウンセリングを行っています。 |
|
| |